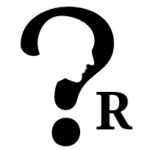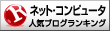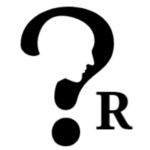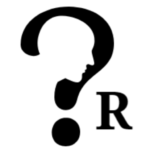「頑張ればどうにかなる。」
この言葉に違和感しかありません。
世の中には多くの仕事が溢れています。
今や機械が介在しない仕事も少なくなってきました。
毎回しないで済むように、システム(仕事の仕方)を作り変えればいいのでは?という考え自体が、当たり前になると思いきや、「お金かかるから無理です」「仕事がなくなるからやめてくれ」という謎が良く発生していました。
前者には、「無くなるような仕事するより、他の仕事した方が意味あるのでは?」、
後者には、「時間の方が大事では?毎日一人にいくら払ってると思ってるの?それはずっと続くんですよね?」と答えたい。
いかに楽ができるか競うことが最優先で、苦労する必要はないでしょう。
何のために頭があるのだろうか。
働き方改革も、皆で頑張れば上手くいくという前提があって、
そもそもこの前提がおかしいのでは?ということに一切触れません。
誰もが生産性高く働く・・・はそもそも生産性が高いようなシステムはどうあるべきか、
そのシステムに何か不備はないか、不備で不幸を被った人はどう救済されるかを議論できていないと思われます。
結局、皆で頑張れば上手くいくから抜け出せていないので。
例えば、「最低時給を1,000円にすると給料を払えない。」、
1,000円すら払えない仕事に、人が基調になっているこのご時世で働かせるの?そんなの不要でしょう。
人を縛り付けている意味が分かっていないです。時間は命だし。
大企業や新興企業の方が、既存の中小企業よりより効率的です。
大企業は規模の経済で財政基盤が強くなりがちで、新興企業はシステム自体が新規です。
異常が出たものが死んでいないのは人体でも異常をきたしそうなのがわかりますよね?
もちろん新しいモノが必ずしも良いとは限りませんが。
特に規模の経済を発揮できない中小企業が増えると人数当たりの生産性が落ちます。
中小企業の数を他国と比べるとどうなのでしょうか。
生産性が落ちれば払える給料も落ちて、その人自体は貧しくなります。
では、その人が買う資金の量は?もちろん減りますよね。
そういった国全体を見た施策が打てているのでしょうか。
個人の生産性を上げようという意味のない言葉や、
「工夫が足りない」「努力が足りない」と言われますけど、その仕事要らないよね?という考えを持つのも工夫や努力ではないのでしょうか。
考えたいこととしては、その事例は本当に要因がわかっているのでしょうかということです。
高度成長は先人たちが頑張って、人が増えたから内需も増えたので購買が増えたのでしょうか。
休日返上で頑張ったから商品が増え、購買が増えたのでしょうか。
人口が順調に増えている国の市場は広がるでしょうか、狭まるでしょうか。
お金は手に入れた分以上使えるでしょうか。
これまではこうだったから。
それは理論から生まれたものなのでしょうか、感情なのでしょうか。
世間とは別の観点が強いのであれば、別に今ある指標を追いかける必要がないのでは?
当たり前だと思っていることは本当に当たり前でしょうか。
感情ではありませんか。