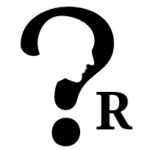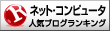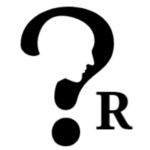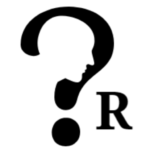仮説1:人は「考えている」のではなく、環境要因によって「考えさせられて」いる。
仮説2:「考える総量」と感情・感覚の量は正比例する。
仮説3:その分野(例:食欲、金銭欲等)が満たされている場合、感情・感覚の量は0に近づく。
仮説4:各分野の「革命的な」発見は、環境によってもたらされた感情・感覚の増大による副産物。
流れ(仮説):気候、地理および歴史的背景→人間への働きかけ→考える総量の増加→知識・技術の発展
今後、人口減少が叫ばれる日本では、不安感、先行きの不透明さが増大していくだろう。
ただよく考えてみてほしい。歴史的に見れば、日本は世界で初めて人口減少を「記録できる」実体験者となる。
そこでは考える総量が増大する。その経験から「革命的な」発見は生まれるだろう。
人口支持力(技術等での人口を維持する力)
人口が増えて最大値に近づけば近づくほど、増加率が減る。最大値を超えると増加率はマイナスになる。=シグモイド関数
発展係数=考えの強度(能力)×時間×人数
※各々の人数は交流しているという前提
※個人の考えの強度は時間を掛ければある程度伸びる前提
係数が高ければ高いほど発展していくスピードが速くなる。
孤高の天才は存在するのか?という話。
ということは「考える必要のない」人々を機械で代替し、
配置転換して「考える」仕事に就かせることで発展係数の総量は増大する。→企業は成長する。
FANUC、トヨタ、ソフトバンク等々は代表的な企業?
歴史での例縄文時代
・早期(約1万2,000 – 7,000年前)に含まれる、7300年前の九州の壊滅。
原因:阿蘇大噴火による。
解決策:九州は住めなかったため東への疎開、定住。定住により集団をより大きくし機能を分け、生存能力を高めた。
・中期(約5,500 – 4,500年前)から後期(約4,500 – 3,300年前)にかけての人口減少。1/3になったと言われている。
原因:地球の温度低下による海面低下、気候変動。それらによる植生の変化により、採取および狩猟や漁獲量が激減。
特に大きく影響を受けたのが東日本。現在より温暖から現在より寒冷になったため、人が住めない土地が増えた。
解決策:トチノキ→ソバへの転向や稲作などの導入。稲作は3500年前ごろからと想定(南溝手遺跡)。
温暖な地域への移住。時を同じくして中国、ゲルマン、アーリア等各民族の移動、エジブト文明やヒッタイト文明などが栄える。
寒冷化による考えさせることの増加
↓
解決策(移動・食文化の変化)
↓
人類の進歩
悪くはないけど、纏まってない文章。